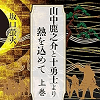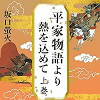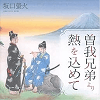ギリシャ神話じゃない!ふたご座の物語~実は曽我兄弟だった!
ふたご座と言えば、ギリシャ神話のカストルとポルックス!でも、実はこの星座は、日本でもある兄弟の星とされていたということをご存知ですか?
「日本三大仇討ち」の一つ、曽我事件を引き起こした犯人、曽我兄弟です。
このエピソードは古典の「曽我物語」にまとめてあります。このページではあらすじを簡単にご説明します!
曽我兄弟、父を殺される

時は鎌倉時代初期。
曽我兄弟は、誰もがうらやむ幸福な家庭に生まれ育ちました。父は伊豆に大勢力を誇る武士、河津(かわず)三郎。美人で評判の母。兄、一萬(いちまん)は色白で優しく、弟、箱王(はこおう)は浅黒く気が強い性格でした。
ところが、兄弟たちの幸福はある日突然崩れ去ることになります。父三郎が、狩りの最中、くせ者によって矢で射殺されたのでです。
三郎を殺したのは、以前から領土問題で争っていた工藤祐経(すけつね)の手先でした。
曽我兄弟、仇討ちを決心する
何も知らぬ子供たちは、門前で父の帰りを待っていました。しかしそこに帰ってきたのは、無惨な父の亡骸だったのです。
その夜、母は子供たちを左右に抱いて語りました。
「二人とも、母の言葉をよく聞き、いつまでも忘れるでない。あのご立派な父上を殺めたのは、工藤祐経です。卑怯者の祐経。この名を胸に刻みなさい。憎い、憎い祐経。お前たち、大きくなったならば、きっと仇を討ってくだされよ」
三つの箱王はまだ何のことか分かりませんが、五つの一萬は顔を上げて返事をしました。
「母上、ご案じなさるな。わたくしがきっと、大きくなって仇を討ってご覧に入れます。これからはわたくしが父上にかわって、箱王を支えます。そして、いつかきっと、父上の無念を晴らします」
この後、父を失った兄弟は住み慣れた家を離れ、母とともに親戚の曽我家に引き取られることになります。曽我の家で育ったので、「曽我兄弟」と呼ばれることになったのです。
富士の裾野で仇討ちを果たす

その後兄弟は元服し、兄は十郎、弟は五郎と名を改めます。
十郎が二十二、五郎が二十歳の年、将軍頼朝が富士の裾野で大規模な狩りを行うことになりました。兄弟は手を取り合い、富士の裾野へ旅立ちます。
そして三日目。ついに祐経の宿を探し当てた二人。
深夜、土砂降りの雨の中、足音を忍ばせ、一番奥の祐経の寝所へ忍び寄ります。何も知らぬ祐経は、泥酔して高いびき……。
十郎が祐経の枕を蹴飛ばし、祐経を起こして叫びました。
「起きろ、祐経!河津三郎の子が、今こそ仇を討ちに来たぞ」
祐経は刀に手をのばしましたが、遅すぎました。兄弟の刀が寝巻の身体に斬りかかり、ついに十八年に及ぶ宿願を果たしたのでした。
十郎、討ち死にする

将軍の寵臣を殺めた者は死罪。初めから、兄弟には生き延びる気はさらさらありませんでした。次々にはね起きて襲い掛かってくる武士たちを相手に戦います。二人合わせて、五十人もの武士を斬ったそうです。(ホントかな?)
兄の十郎はその戦いの中で討ち死に。
「五郎! 五郎はなきか。我は新田四郎の手にかかって討たれる。死出の山にて待つぞ」
兄の最期の叫び。五郎は太刀振り回して、死骸なりとも今一目顔を見んと、垣根の如き武士たちをかき分け走り寄ります。
「恨めしや、五郎を置いて――。わたしを捨ててどこへ行く。兄者人、共に連れて行け……」
兄の死骸に縋り付いて、声を放って泣いたのでした。しかし、襲い掛かる武士たちの無情の手。五郎はなおも勇ましく戦いましたが、後ろから組み付かれ、無数の手に捕まって、無惨にも縄で縛られ生け捕られたのでした。
五郎、死罪となる
五郎は一人、将軍の前に引き出されます。将軍直々に尋問されますが、少しも遠慮せず、思うさまに述べるその態度は、実に堂々たるもの。
「助けてやりたい」
と頼朝は言いましたが……半身とも頼む兄を失った五郎は、もう生きるつもりはありませんでした。
「兄者人のいないこの世に、どうして生きていけよう。こうして、一時たりとも長く生かされていることこそ、恨みに思っている。今はただ、一刻も早く首を斬れ」
五郎は、からからと高笑いしながら首を打たれたのでした。
星になった曽我兄弟
というわけで、お亡くなりになってしまった曽我兄弟。
ですが、その人気たるや不滅。ふたご座の一等星、カストルとポルックスに「曽我兄弟の星」と名付けられたのでした。この二つの星、片方が金色、もう片方が白いので、「五郎は色が浅黒く、十郎は白かった」という曽我兄弟にピッタリですね。
ところでこの二つの星、日本は広いですから、地方によって色々名前があります。「カニの目」「猫の目」「二つ目」というおメメシリーズ、「ひな祭りの星」というカワイイの、「金星、銀星」なんてロマンチックな奴、「二つ星」なんてそのまんまの奴まで、種々様々!
でもやっぱり、わたしはこの星を「兄弟」に見立てるのが、一番ピッタリな気がしますよ。
まとめ
遠いギリシャと日本で、いずれもふたご座が「仲の良い兄弟の星」とされているのは、なんとも不思議な偶然です。ひょっとしたら、シルクロードを通じて「兄弟の星」という話が伝わっていたのかもしれませんね。
皆さん、冬の夜空にふたご座を見つけたら、ぜひとも曽我兄弟に思いをはせてみてください!
↓曽我兄弟について、もっと知りたい人はこれを読むのだ!
古典専門ブログ、「古典ログ」でも曽我物語を紹介してます。こちらも見てね。
【関連記事】
ギリシャ神話じゃない!さそり座の物語2話